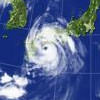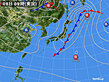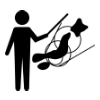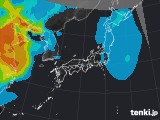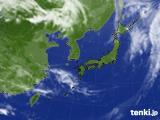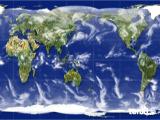海上保安庁の巡視船の船舶料理士として勤務した経験を生かして暮らしに役立つ情報を発信する川崎みささんは、2018年の西日本豪雨の際、まったく備えをせずに自宅で被災。「子供達の被災期間をより過酷にしてしまった」という反省から、災害への備えを学び、「ひろしま防災Jプログラムトレーナー」の資格を取得。そんな、2児のママでもある川崎さんに、「わが家の備蓄」について教えてもらった。
文・写真=川崎みさ
船舶料理士は『ワンピース』のサンジ
私は海上保安官として巡視船に乗り組んでいました。巡視船は、海の治安を守ることが仕事。密漁者などが現れたら取り締まり、海難事故があれば救助に駆け付けます。私はそこで、船舶料理士として働いていました。
船舶料理士とは、「船の上の料理人」のこと。海賊王を目指すルフィが主人公の『ワンピース』で言えばサンジです。
わたしもサンジと同じように、普段は巡視船の乗組員のために食事を作り、密漁者が現れたらエプロンを脱ぎヘルメットと防弾チョッキを装備して、一晩中密漁者を追いかけていました。
備蓄の必要性を痛感した西日本豪雨
恥ずかしながら、2018年の西日本豪雨で被災した時、わが家には備蓄がほとんどありませんでした。なぜなら、夫婦ともに海上保安官だったので「災害が起こったら出動する」イメージがあり、家に何かを備えるという発想がなかったのです。そのせいで、7月の暑い時期に起こった西日本豪雨では飲み水はもちろん、食べるモノにも困り、被災期間をより過酷なモノにしてしまいました。
この大失敗から、家に災害用の備蓄をしようと思い、何をどう備えたらいいのか試行錯誤する中で、思い出したのが海上保安官時代に船舶料理士として働いていた経験でした。
私の勤務していた大型巡視船は、2週間から1カ月ほどの長期航海をしていました。あまり知られてはいませんが、船内には常温で長期保存ができる食品や乾物を必ずストックしています。緊急出航や事件・事故による任務期間延長時でも、命がけで働く乗組員や救助した方々に食事を提供するためです。
これを、家庭用の防災備蓄として応用しようと思い、巡視船でやっていた3つのポイントを押さえながら、防災備蓄を揃えました。
海保式防災備蓄の3つのポイント
【ポイント1】作り慣れている
作る手順が分かっていると、いざという時も失敗して食材をムダにすることがありません。非常時は、あたふたしているので「作り慣れている」はとても大切です。
【ポイント2】食べ慣れている
非常時はただでさえ混乱しているので、食事くらいは「いつもの味」でホッとしたいですよね。実は、西日本豪雨で唯一、家にあった「乾パン」を5歳の娘に食べさせようとしたところ、初めて乾パンを見た娘から嫌がられてしまいました。「食べ慣れている」は、本当に大事だと再認識した出来事です。
【ポイント3】どこでも買える
スーパーやドラッグストア、コンビニで売っているものだと、買い足しのハードルが低いので「買って・食べて・買い足して」のローリングストックがしやすくなります。また、値段が高すぎるものは買ったり食べたりするのをためらってしまうので、なるべく手頃な値段のものを選んでいます。
何をどのくらい備える?
防災備蓄で悩むのが「量」ですよね。多ければ多いほど安心ですが、収納スペースにも限りがあります。また、量が多すぎると消費期限などのチェックが大変になることもあり、4人家族のわが家では引き出し2つ分の防災備蓄(3日分ほど)に5キロの無洗米(1週間分)を備えています。
海上保安庁の巡視船でも、「最後は米さえあればなんとかなる」と多めに積んでいたので、被災後からお米のストックは欠かさないようになりました。
そして、巡視船で船舶料理士として働いていた頃に、先輩方から口を酸っぱくして何度も言われていたのが「栄養バランスを考える」こと。限られた食材や予算の中でもバランスがとれるように、炭水化物やタンパク質だけでなく、野菜ジュースや小魚のおやつでビタミンやカルシウムを取れるようにしています。
また、個装の栄養補助食品、レトルトのお粥、魚肉ソーセージ、ゼリー飲料など簡単に食べられる備蓄があると、さらに防災力がアップ。
なぜなら、災害時にケガをしたり体調不良のために食事作りができない場合もあるからです。西日本豪雨で被災したとき、私が産後1カ月で思うように身体が動かなかったこともあり、念のため手軽に食べられる食品も備えています。
最後に水について。西日本豪雨で被災したとき、真夏に約1カ月の断水になり、水の確保に本当に苦労したので、わが家では、ペットボトルの水を6箱(72リットル)と600mlのお茶を3箱(43リットル)の約100リットルを備蓄しています。
飲料用・調理用として1人当たりに必要だと言われる1日3日リットル×家族4人分の1週間分よりも少し多めに備蓄している理由は、西日本豪雨の際に産後1カ月だったこともあり、周りの方に助けていただくばかりだったので、今度はわたしが誰かの力になれたらいいなと思い、いざという時に「おすそ分け」ができるようにしているためです。
防災訓練でローリングストックを回す
全ての防災備蓄をローリングストックできるのが理想ですが、なかなか使わないものもあるので、わが家では夏休みや冬休みなどの長期休暇に子ども達と一緒に防災訓練を兼ねて防災備蓄を食べるようにしています。
また、子どもの急な発熱時には備蓄品のレトルトのお粥やゼリー飲料が大活躍!体調不良の子どもを連れての買い物は大変なので、とりあえず家にある備蓄品を食べさせ、子どもの体調が回復してから消費した分を新たに買い足しながらローリングストックをしています。
普段は、スーパーやコンビニで簡単に手に入る水や食料が、災害後には手に入らなくなります。災害の影響でお店が開けられない場合や、自分が大きなケガをして買い物に行けない場合も。そんな時に、役立つのが「防災備蓄」です。
わが家は西日本豪雨で被災したとき、備え不足のせいで災害期間をより過酷なものにしてしまいました。わたしのような大失敗をしないためにも、いざという時に役立つ防災備蓄を家に備えてくださいね。
川崎みさ(かわさき・みさ)
1985年生まれ、広島県在住。元海上保安官で2児のママ。船舶料理士、整理収納アドバイザー1級、ひろしま防災Jプログラムトレーナー。