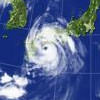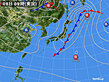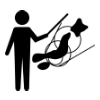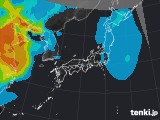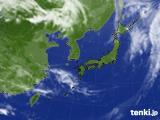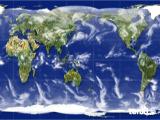誰もが一度は目にしたことのある、赤いポール。そして、丸い看板に白い文字で「消火栓」と書かれた標識。
これは、「ここに消火栓がありますよ」と示すための標識だ。「家の近くにあるかも」と思う人はいるだろうが、「こことここにある」と言える人は少ないかもしれない。
この消火栓標識の多くは、実は民間が維持・管理している。
主に都内などで設置・維持管理等を行う消火栓標識株式会社を訪ねた。
そもそも消火栓標識って?
消火栓標識は、消防隊員や地元の消防団が火事などの際、消火栓の位置をいち早く見つけるために設置されているもの。
駐車されたり物を置かれたりすることを防いだり、積雪時の目印になるという役割もある。
消火栓標識株式会社は、例えば東京都の場合、東京消防庁らと協力しながら、標識を建てるための許可を取り設置、維持管理しているという。
「あまり目に入る人は少ないですが、標識には白い矢印がついています」
「その矢印の先の地面に黄色い線で囲われたマンホール型(地下式)消火栓があります。火事のときはそこから水を引きます。白い矢印に書かれている数字は、消火栓までの距離です」
80%の標識に広告なし
そう語るのは、消火栓標識株式会社の代表取締役で、全国消火栓標識連合会の理事長を務める毛利綱作さん。
東京、埼玉、千葉、神奈川といった関東圏から、静岡や愛知、山形、宮城の消火栓標識を維持管理している。東京で約2万5千本、埼玉と千葉でそれぞれ約4000本などと、その数なんと約6万本だ。
「設置する際に関係各所からの許認可を得ますが、基本的には弊社で維持管理しています。その方法が消火栓標識の下に広告を入れることです。その費用で標識を新たに建てたり、建て替えたり、数年おきにペンキを塗り直したりしています」
管轄内の消火栓標識約6万本のうち、実際に広告が入っているのは現在1万本程度。
約80%の標識に広告が入っていないという。長方形のフレームだけになっている標識を見かけたことがあるはずだ。
70年前は先進的だった
毛利社長は「弊社は創業から70年ですが、創業時、消火栓の近くにポールを立てて、税金で賄うのではなく民間で広告を入れて行うことは、とても先進的だったと思います」と語る。
広告の主な使われ方は、「ここから先20メートル」といった店舗などへの案内表示で使われたり、病院等の電話番号が掲載されたりしている。長いものだと50年近く、広告を掲載している企業・施設もあるそうだ。
昔は多くの人がこうした広告から情報を得ていたが、昨今スマホなどから得られる情報が増え、街中には消火栓標識以外の看板も圧倒的に増えた。
「地元に根ざした企業や施設だけではなく、実はロゴだけでわかるようなコーヒーチェーン店も都内の主要駅で広告を出したりしています。さりげなくロゴ等を出すことで『ここに店がある』などということを上手に印象に残せるのです」
さらにいま、「地域密着型」の企業と連携するといった、新しいカタチの使われ方を展開している。一つの事例として、プロサッカーチーム「東京ヴェルディ」や「モンテディオ山形」などがオフィシャルパートナーとなり、チームのロゴとパートナーを組む地元企業のロゴ等を入れて広告を作る、といった取り組みもしている。
早ければ1カ月くらいで掲載
ちなみに、標識にぶら下がる長方形の広告は、フレームを除いて縦36センチ×横76センチ。近くで見ると意外と大きく、それらはアルミ板に自社で印刷している。両面印刷で、1時間ほどでできあがる。
看板デザインが決まれば早いそうで、申し込みから1カ月程度で広告を載せることができるという。
文字だけでなく、印刷技術も発達したことで、写真も入れることができるようになった。景観に関するルールが定められている自治体もあるが、基本的に制限はなく、公序良俗に則っていればどのようなデザインも可能とのこと。
新しい標識は年に数十本ほど建つことがあるようで、麻布台ヒルズにも建てる予定だという。
ただ、毛利社長の一番の思いは、「いざというときに役立つために」というところにある。
「消火栓標識があるところに車を止めない。荷物を置かない。それを知ってほしいです。実際に全国で火事が起きた際に消防隊員が、消火栓を開けられないことがあるのです。もちろん我々としてはビジネスでもあるので、広告が入ることも大切ですが、消火栓標識と消火栓の認知を広げることも必要だと考えています。そのために標識を抜くことなく、維持管理しているのです」
とある商店が消火栓のマンホールの上に陳列していたりする場面を見たこともあるそうだ。
「消防隊員が場所を把握していても、消火栓が隠れていたら探す時間が生まれ、物を置いていたらどかす時間も。こういうことは全国であって、たまたま火事がないだけ。でも、なにかあって初めて気づくのです」
役に立たなくなることを防ぎたい
「でも、地面にはたくさんマンホールがあって、どれが消火栓かなんてわからないですよね」と毛利社長。だからこそ、より多くの人に目印となる「消火栓標識」の存在を知ってもらいたいと訴える。
大きな災害も増え、人々の防災意識が高まっている。とは言え、防災に関して、まだまだ知らないことがあるのが現状だ。
「役に立つことより、消火栓標識や消火栓が機能しなくなることを防ぐことも大切なこと。『ここで消火栓標識が役に立ちました!』という実感がないだけで、有事の際の目印になっていることは間違いありません」
危機があって初めて、必要だった!と意識することもあるだろう。家の近くにある消火栓標識の場所を知る、それだけでも自分の街の防災につながるはずだ。