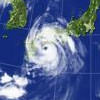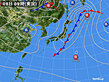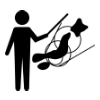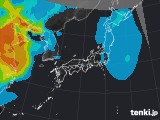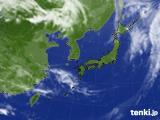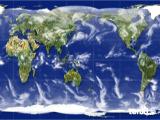旧暦十月十日の夜には「十日夜(とおかんや)」と称する民間行事があります。東日本、特に新潟、長野、山梨から北関東にかけて盛んで、春の耕作の開始時期から田畑に立って作物を見守ってきた案山子(かかし)を引き上げ、作物神の依代として、畑の作物や餅を供えます。また村落の子供たちが「藁鉄砲」と呼ばれる稲藁を束ねて縄でぐるぐると縛って棒状にした呪具をもち、村の道を叩いてまわります。
十日夜は別名「大根の年取り」と言い、西日本にはほぼ同じ行事が旧暦十月の亥の日の「亥の子」として伝わります。こちらは藁鉄砲ではなく、石で道を叩いてまわります。
藁鉄砲や石で道を叩く理由は、民俗学では「大地の精霊に活力を与える」などと説明されていますが、そうでしょうか。悪霊ならともかく、精霊(神)をひっぱたいて活力を与えるなどという乱暴な信仰はあまり聞いたことがありません。
古語で「なふ(なう)」とは「平ふ/均ふ/正ふ/直ふ」であり、でこぼこの土地を平らにならす、もとの状態に復元する、という意味になります。
十日夜の地面を叩く行事は、春以来土を掘り起こし、耕作をして大地を荒らした営みの終わりに、土を均(なら)し、自然本来の状態にリセット(掃除)する意味ととらえるべきではないでしょうか。
「神(かみ)」(カミ/クマ/カム)という和語の語源は、「被(かむ)る」「隠(くま)る」などの意味で、山や森、谷の奥や洞窟などの人の足が及ばぬ奥地に隠れていて、水や光などの霊力を送り込む力/作用のことでした。「山」「闇」「谷津」に隠れているカミは、卯月八日、村人たちの迎えに応じて里に降りてきて歓待を受け、田畑に留まり、耕作の手助けをすると信じられていました。そして十日夜、亥の日をもって、丁重に送られて山へと帰って行くのです。
つまり「神=隠+直る」で「かむな(かんな)」です。わざわざ里に降りてきて人のために手を貸していた隠=カミが、この行事をもって本来の隠れた聖所に「直る(戻る)」のです。
古語ではヤドカリのことも「かむな」と言います。巻貝の秘所にひきこもるこの小さな甲殻類のように、神が本来の見えない聖なる存在となる、その時期を「かんな」とあらわしたのではないでしょうか。そしてそれはそのまま、生物の活動が停止・低下する冬の季節の到来を意味したので、神々の母であるイザナミの命日も、この月になったと言えるのではないでしょうか。
参考・参照
日本書紀 日本古典文学体系 岩波書店
佐太神社 神在祭(お忌さん)