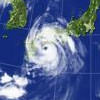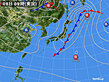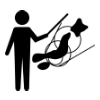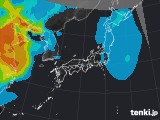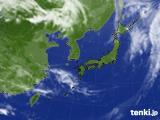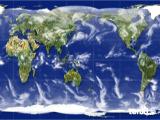「ガリオア・エロア資金」を知っている人はどれくらいいるでしょう。これは第2次世界対戦後に、アメリカが占領国に対して行った援助資金のことで、日本は1946年から6年間で18億ドルの支援(13億ドルは無償)を受けています。これは当時の金額で約12兆円にもなり、日本の復興を支える資金となっています。
さらには1953年から1966年までの間、世界銀行から復興支援として合計8億6,290億ドルを借りています。この資金は黒部第四水力発電や東海道新幹線、東名高速道路、名神高速道路、愛知用水など、日本のインフラを支える開発に使われています。
このように戦後、様々な形で支援を受けたことが日本の発展に繋がっており、経済支援の重要性を身にしみて知っている国だからこそ、自国の経済が悪化したときでも、日本は積極的にODAや海外協力隊の派遣を続けてきたというわけです。
自分たちが支えてもらったのだから、次は支える側になる。それによって地域の経済格差がなくなり、日本などの支援によって開発途上国を卒業した国が今度は支える側になっていきます。実際に中国やインドといった国はすでに援助する側になっています。
こうして世界の経済格差が埋まり、ゆっくりとでも貧困問題が解決していく。そう思うと、自分たちの税金が国際協力に使われるのも理解できますよね。今の日本があるのは国際協力のおかげで、未来の経済格差のない世界も国際協力があってのこと。
個人でできることはそれほど多くありませんが、せめて国際協力の日くらいは日本がどのような支援を受けてきたのか、そしてどのような支援をしているのかを話題に周りの人たちと話をしてみてはいかがでしょう。
【参考】
国際協力の目的について|JICA日本の戦後復興|外務省