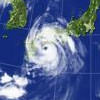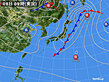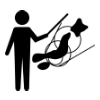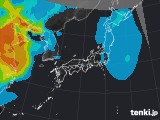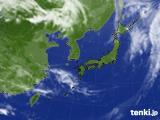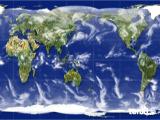梅は中国原産の花ですが、日本では奈良時代から栽培され始めたといわれています。江戸時代、武士の間で梅園芸が大ブームとなり梅の文化が花開きました。
梅見で有名な水戸の偕楽園は、江戸幕府最後の将軍慶喜の父、水戸藩第九代藩主・徳川斉昭によって造園されました。江戸時代に品種改良が盛んに行われ、現在偕楽園は約100品種・3000本の梅の名所として、毎年梅まつりが開催されています(今年は2月15日(土)~3月29日(日))。
早咲きの梅を一輪一輪探しながら楽しむことを「探梅」、咲きそろった梅を楽しむことを「賞梅」、散りゆく梅を惜しみながら愛でることを「送梅」というそうです。このように、春を待ちわびつつ、段階を踏んで変化を楽しみ観賞するのが梅見のポイントです。
中でも、江戸の伝統を引き継ぎ、香りや色、形が優れた六品種が『水戸の六名木』とされています。それぞれの特徴を知っているとさらに観賞が深まりますね。
〇虎の尾(とらのお)
八重咲きの中輪で、開き始めが薄紅色。開花後白くなるのが特徴です。
〇江南所無(こうなんしょむ)
明るい紅色の厚い花弁、大輪で雌しべを抱え込むように咲くのが特徴です。江南地方(中国)にこれ以上の梅はないという意味で名付けられたという説があります。
〇烈公梅(れっこうばい)
烈公は徳川斉昭の別称で、斉昭公にちなんで名付けられたもの。蕾は濃いめのピンク、開くと薄紅色の大輪で、一重咲きです。
〇月影(つきかげ)
よい香りが特徴です。また明るいグリーンの蕾と、さわやかな白梅の花びらの輪郭が美しく豪華です。
〇白難波(しろなにわ)
やや早咲きで白い中輪の花を楽しめます。ほころんだときの微かな淡紅色が開花したあとも花の外側に残るのが特徴です。
〇柳川枝垂(やながわしだれ)
一重咲きの薄紅色中輪。つぼみは濃紅色の萼(がく)に包まれていますが、開花すると萼は反り返り、淡紅色の花弁が現れます。
参考:
茨城県ホームページ偕楽園ホームページ