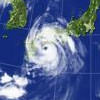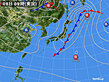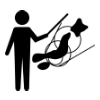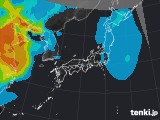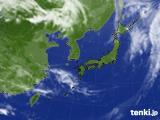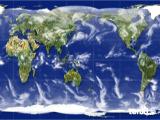近年、日本列島では気象災害も頻繁に起きている。
「ゲリラ豪雨」「線状降水帯」という言葉を耳にする機会も増し、さらに「竜巻」に関する報道も増えてきた。
京都大学名誉教授で地学の第一人者・鎌田浩毅さんの著書『災害列島の正体――地学で解き明かす日本列島の起源』(扶桑社)から、これまで起きた日本での竜巻被害と予兆について一部抜粋・再編集して紹介する。
意外と日本でも多い竜巻被害
最近の日本では竜巻の被害報道が多くなった。竜巻とは上空にある雲から、じょうごの形をした細長い雲が地表まで達して、突風をもたらす現象である。
非常に強い渦を巻いた風が吹き荒れ、地上の物を巻き上げる。その結果、通過する地域に大きな被害をもたらす。
竜巻は季節を問わず起きるが、特に台風シーズンの9月に多く発生する。気象庁によれば、2007~2023年の平均で1年あたり約20件(海上竜巻を除く)の竜巻が起きている。
2012年5月6日、茨城県つくば市内で発生した竜巻は死者1人(家にいた中学生)、負傷者37人、全壊家屋89棟、半壊家屋242棟、一部損壊家屋384棟という凄まじいものだった。
竜巻の被害は「藤田スケール」で表す。藤田スケールとは米国シカゴ大学の藤田哲也博士(1920~1998)が導入した竜巻や突風の強度の分類法で、数字が大きいほど風速が大きかったことを示す。
地震で言えば震度のようなものだ。気象学者の藤田博士は、竜巻研究の世界的権威で“ドクター・トルネード”の異名を持ち、「藤田(F)スケール」は世界中で使われている。
ちなみにFスケールは6まであり、日本ではF4以上の竜巻や突風は観測されていない。
これまでF3を記録した突風被害には、2006年11月7日に北海道佐呂間町で発生した竜巻がある。この竜巻によって、工場のプレハブ小屋にいた9人の犠牲者を出し、31人が重軽傷を負っている。
建物の被害も、100棟以上に及んだ。2020年7月に埼玉県三郷市で発生した突風も竜巻と確認され、人的被害はなかったものの、住宅の屋根などに被害が発生した。
F3の竜巻は5年に1回程度の頻度で日本のどこかで発生している。
完全に解明されていない竜巻
竜巻の発生メカニズムは非常に複雑で、現在でも完全には解明されていない。だが、台風と同じように、大気の渦が引き起こす強風であり、キーワードはいずれも上昇気流である。
地面が温められると上昇気流が発達し、積乱雲が発生する。上空で水蒸気が水滴になると、周囲へ熱を放出し、積乱雲の周囲にある空気を温める。
この結果、温められた周りの空気ものぼりはじめ、上昇気流が強くなる。
こうした状況で暖かく湿った空気が流入してくると、上昇気流はさらに強くなる。このとき、気流は地球の自転を受けて激しく回転しはじめ、竜巻が発生することがある。
気流の回転が螺旋状に渦を巻きながら、短時間に巨大な竜巻へと成長していくのである。
竜巻の予兆と避難
2006年9月に宮崎県延岡市で発生した竜巻は、わずか5分の間に長さ7キロメートル幅300メートルの範囲に大きな被害をもたらした。竜巻はときに、時速90キロメートルもの高速で移動する。
そのため、被害がどの方角へ広がるのか、予測がかなり難しい。最近ではテレビなど報道機関でも竜巻が発生しやすい気象条件になると注意報が報じられるようになった。
竜巻が近づいてきたときには急に空が暗くなり、雹(ひょう)がバラバラと降ってくることがある。
また、雲の底からじょうご状の雲が垂れ下がっていたり、飛行機に乗っている時に気圧の変化を耳で感じるのと同じ感覚を覚えることもある。それぞれが竜巻の予兆のひとつである。
その後、黒い雲が地面から立ちのぼり、渦を巻きながら移動する。大型の竜巻が発生すると、建物の屋根や自動車が吹き飛ばされ、列車が横倒しになることもある。
また、上空へ巻き上げられた物体は、通過地点に次々と落下し、大きな被害を与える。そして最後に、竜巻は降雨とともに数十分で収束する。
竜巻のように突然襲ってくる災害は、事前の避難が困難である。そのため、竜巻に襲われた際に身を守る方策を知っておく必要がある。
まず、竜巻が近づくと気圧が急に下がるため、窓ガラスが割れることもある。そこで雨戸やシャッターを閉め、カーテンも閉めておく。2階にいる場合は階下へ移動し、机の下に潜って毛布などで頭を守る。
また、屋外にいる場合には、近くにある鉄筋の建物内へ直ちに避難する。
もし車の運転中であれば、風が強くなる橋や陸橋に近づかないようにすることが大切である。同時に飛来物にも注意が必要だ。
気象庁は竜巻が今から発生する可能性をリアルタイムで推定して「竜巻発生確度ナウキャスト」として発表している。一人ひとりが身を守るために活用したい。
鎌田浩毅
1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。理学博士。通産省(現・経済産業省)を経て1997年より京都大学大学院人間・環境学研究学科教授。京大の全学向けの講義「地球科学入門」は毎年数百人を集め、「京大人気No.1教授」としても名高い。2021年より京都大学名誉教授および京都大学経営管理大学院客員教授。専門は火山学、地球科学。