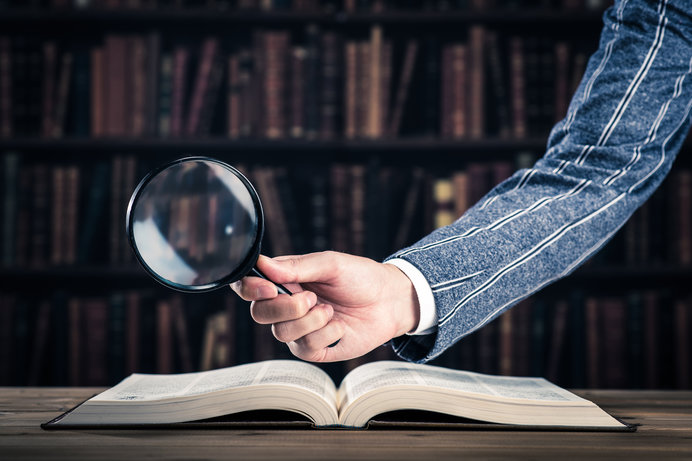日本では神田孝平が明治20(1887)年、犯罪実話録であり推理ものの原型の一つともされる「和蘭美政録」を翻訳出版。そして明治23年、「岩窟王」や「レ・ミゼラブル」などを翻訳紹介した黒岩涙香(くろいわるいこう)が1889年、自身の著作「無惨」の序文で、この小説を「探偵小説」であると紹介し、日本初のミステリーの皮切りとなりました。以降「探偵小説」という呼称は幻想怪奇小説やSF小説をも含む広い「謎解き娯楽もの」の総称ともなりましたが、名探偵が登場するミステリーも長く「探偵小説」と呼ばれ続けます。大正13年には、「病める薔薇(そうび)」などを著した小説家・詩人・翻訳家の佐藤春夫が、欧米の長編ミステリーを「本格探偵小説」と名づけました。
そして大正12(1923)年、「二銭銅貨」で一人の推理作家がデビューします。エドガー・アラン・ポーの名をもじった江戸川乱歩です。乱歩のバタ臭くけれん味のある世界観は、大正デモクラシーの洋風趣味や昭和初期の金融恐慌に端を発する社会の不安や退廃を反映した、猟奇的で幻想的、エロティックな作風で、大いに人気となります。乱歩の担当編集だった横溝正史は、乱歩の断筆を引き継ぐように、日本的な土着の「村」の恐怖を取り入れ、欧米で創出された「密室トリック」などの仕掛けが作りづらい日本家屋を逆手に取り、因習や禁忌、地形をトリックに利用し、日本独自の本格ミステリーを確立しました。
「推理小説」という言葉が生まれたのは戦後のこと。昭和21年、内閣訓令により「当用漢字表」が告示され、公的に使用できる漢字が限定されたことによります。「探偵」の「偵」という漢字が当用漢字に含まれなかったため、戦前甲賀三郎が探偵小説とは一線を隠す意味で一時期使用した「推理小説」が、代用語として突如使われるようになったのです。
ところが戦後、乱歩の耽美的洋風の世界観、正史の土着村社会的世界観とに支えられた日本の本格ミステリーは昭和30年ごろを境に衰退します。世は高度成長とサラリーマン社会。社会派ミステリーと呼ばれる都市文明の中で起きる陰謀やビジネス戦争、人間の軋轢、社会問題を主眼に置いたストーリーをつむぐ松本清張、高木彬光、水上勉、黒岩重吾などが大人気を博し、推理小説の主流となります。
やがて衰退していた本格推理も、綾辻行人が1987年「十角館の殺人」でデビューすると、再びニューウェーブ(新本格派)の書き手が押し寄せるようになりました。「十角館の殺人」は、アガサ・クリスティ以来の典型的クローズドサークル(孤島や雪山などのとどされた館に人々が閉じ込められて起きる殺人事件)が展開され、本格推理の形式が時代を超えて復活した金字塔です。
あざとさ満載の名探偵も、ご存知の通り古い作品を知らない世代にはむしろ新鮮さをもって受け入れられ、古畑任三郎や杉下右京などのテレビドラマの名探偵(彼らは肩書きは刑事ですが、実質はデュパン以来の名探偵の系譜に連なるキャラクターです)や、有栖川有栖の江神二郎、京極夏彦の中禅寺秋彦など、ポーが創出し、ドイルがふくらませた「名探偵」というキャラクターが、時代を超えて通用する不滅の発明であることを証明し、驚嘆させてくれます。
ついでではありますがかく言う筆者自身も、かつて本格推理の作品を手がけました。諸般の事情で二作で打ち切りとなりましたが、実は前二作を超える出来の、ウンベルト・エーコの「薔薇の名前」の世界さながらの第三作が用意されていました。もしいずこかで描かせてもらえるのなら日の目を見るのですが…。
神田孝平「和蘭美政録」(明治文化全集)