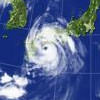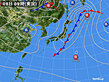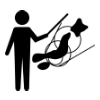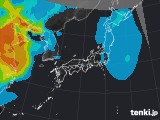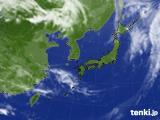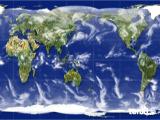それにしても、開戦の報に感激し、高揚して一気に書き上げた、という「星月夜」にはどこか違和感を感じます。たしかに「里の秋」で改変された際に削除された三番、四番には子供たちを鼓舞する歌詞を作ろうという斉藤の意思はよく表れています。が、残された一番、二番の、「背戸(裏口)に木の実が落ちる」「鳴き鳴き(泣き泣き)夜空を渡るカモ」など、歌詞は不安や不吉を暗示するワードで占められ、高揚感や勇ましさはまったく感じられませんよね。
皇国教師の表向きの建前や信念とは対極的な、心の奥底にある何事もない平和な日常への愛惜の気持ちと、それが阻害される戦争への不安が、作者の意識を裏切って滲み出しているように思えます。だからこそこの歌の前半は、ほとんど変更もなくそのまま「里の秋」として転用されたのです。
二番や三番も悪くはないのですが、やはり飛びぬけて秀逸なのは一番の歌詞でしょう。ドングリでしょうか、裏口の戸のあたりにポツン、と木の実の落ちる音さえ聞こえてくる秋の村里の静かな夜。パチパチとわずかにはぜる囲炉裏のおき火と、ふつふつと煮える鍋の音。
特に注目すべきは、「栗の実煮てます 囲炉裏端」という部分。「煮てます」と言う敬語と倒置法という変則文法の組み合わせは、さながら現代俳句/短歌や広告コピーを見るような現代性や新しさ、はっとする意外性を感じさせます。さらに、一番・二番で登場する栗が日本の国土の象徴、対して椰子が戦地であった海の向こうの南島の象徴となり、鮮やかな対比を生み出しています。こうしたモダンな技巧を用いながらも、この詞は古典性も併せ持ちます。「ああ とうさんのあの笑顔 栗の実食べては思い出す」という歌詞は、山上憶良の万葉集の有名な長歌と対応します。
瓜食(は)めば 子供思ほゆ 栗食めば まして思(しの)はゆ(山上憶良 万葉集巻五 802)
万葉集では父が子供を思いながら栗をかじっていましたが、「里の秋」では子供が父を思いながら栗を食べています。千年の昔から日本人がはぐくんできた家族愛、親子愛。「里の秋」は素朴な田舎の温かさと洗練された教養、古典性と現代的感覚が同居して成立した名詞です。
斉藤は、北原白秋、西条八十、野口雨情、三大童謡詩人を尊敬し、研究していましたが、中でも「生まれ育った風土が近く、一番しっくりする」と雨情を敬愛していました(雨情は房総と気候風土が似ている茨城の出身)。けれども、「里の秋」の後の斉藤のヒット作「蛙の笛」「夢のお馬車」、あるいは童謡としてのデビュー作「ばあや訪ねて」などを見ても、作風としてより近いのは、雨情の明示し難い不条理に彩られた感覚的な作風よりも、こまやかな技巧と合理的な抒情を詠う西条八十のように思われます。
斉藤は、戦後しばらくの浪人生活の中で童謡詩作に打ち込み、やがて気を取り直して中学教師として再出発した後にも、月刊童謡誌「花馬車」を刊行、数多くの作品を残して児童教育、童謡の発展に尽力しました。作った童謡の数は1万1227作。
ちなみに、世間の高評価とは逆に「里の秋」の三番は斉藤自身は気に入らなかったらしく(戦死した兵士の家族の中にはこの歌の内容で悲しみを深くしたというエピソードもあったためといわれます)、オリジナルバージョンの「里の秋」も後に作っています。それは、「戦争がなかった日本」を夢想したような、帰りの遅い父を無邪気に待つ、平行世界の子供と母の情景。斉藤にとって戦争が消えない悔いとしてどれほど深く刺さっていたかをうかがわせます。
「里の秋」の作詞者・斉藤信夫が生涯暮らした千葉県山武市も、先の台風で大きな被害を受けたようです。千葉県、そして伊豆諸島の被災地に、穏やかな秋の日が一日も早く戻ることを願います。
里の秋 川田正子