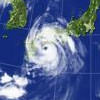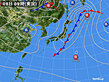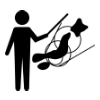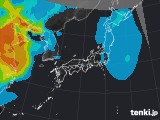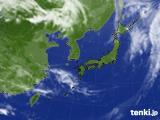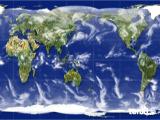さて、春分が近づく三月ともなると、咲く花の種類もぐんと増えだします。梅や水仙は言わずもがなですが、梅雨時の梔子(クチナシ)、仲秋の金木犀(キンモクセイ)とともに、三大香木のひとつとされる沈丁花(じんちょうげ)の花の強い芳香にお気づきでしょうか。
貝原益軒は『大和本草(1709年)』で「香遠し故に七里香とも云」と、離れた場所にも届く強く甘い芳香について言及しています。クチナシやキンモクセイよりもシトラス系の香りが強く、甘さとともに爽やかさもあわせ持ちます。
沈丁花(Daphne odora)は、ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属の常緑低木で、原産地は中国南部付近と推測され、日本には中世ごろに渡来し、庭木として好んで植えられました。十字型の四弁花に見えますが、花弁に見えるものは花弁状に発達したがく裂片で、花弁はありません。がく裂片の外側が濃い赤紫、内側が白色で、このコントラストが独特の色味と模様を作り出し、20個ほどの花が集まった球状の花房が開くと、まるで小さな鞠のように見えます。
「沈丁花」という変わった和名は、東南アジアに生育する香木「沈香」の香りに似ていること(沈香自体がジンチョウゲ科ですから、当然といえば当然ですが)と、カレースパイスのひとつして有名なクローブ(丁子/ちょうじ)と似た花をつけることから。種名のDaphne(ダフネ)は、ギリシャ神話で、太陽神アポロンに見初められた美しい妖精ダフネに由来します。ダフネはアポロンから逃げるために月桂樹の木に変容したという神話がありますが、なぜかジンチョウゲ科の科名がダフネになっているのは、ちょっとした謎です。
謎といえば、ネットのフリー辞典などでは、沈丁花は雌雄異株(雄花をつける木と雌花をつける木が別であること)で、日本には雄株しかない、といった記述が見られますが、これは間違いで、花には雄しべと雌しべがきちんとそなわっています。沈丁花は両性花です。沈丁花がほとんど結実しないために、このような思い込みがどこかで発生し、検証されないまま広まったのかもしれません。おそらく古い時代に人為的に作出されたため、結実性がほとんど失われたものと思われます。しかも、中国での原産地も不明で、原種となる野生種も見つかっておらず、その栽培の歴史も謎のままです。
ジンチョウゲ科の草木は、樹皮を形成する靭皮(じんぴ)繊維が長く丈夫なため、多くの種が紙の原料となります。和紙の原料となるミツマタ(三椏)やガンピ(雁皮)はその代表ですが、特にミツマタは三月ごろから白とレモン色の変わった花を樹冠いっぱいにつけ、花も大いに楽しめます。
(参考)
新訓萬葉集 佐佐木信綱編 岩波書店
歌集「錨」 白木康治 行人舎
植物の世界 朝日新聞社
誹諧新式目 / 鷺水