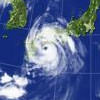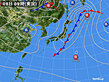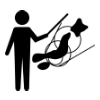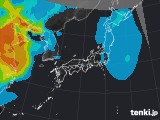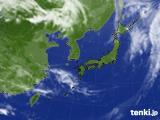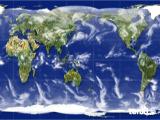「女性差別撤廃条約」は、1979年の国連総会において採択され、1981年に発効、日本は1985年に締結しました。それを受けて、1986年に「男女雇用機会均等法」が施行されました。事業主が募集や採用、昇進、福利厚生、退職、解雇などにおいて、性別を理由に差別することを禁止する法律です。
施行当初は各種差別禁止の項目の多くは努力規定でしたが、1997年の改正でようやく禁止規定となりました。2007年の改正で、出産・育児による不利益取扱の禁止や、セクシャルハラスメントの禁止などが規定され、2017年の改正ではマタニティハラスメントに対する禁止規定が追加されました。
「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」といった、すべての子どもが持つ権利を保障するための「子どもの権利条約」。1989年に国連総会で採択され、現在196の国と地域が締結しています。日本では、1994年に158番目の国として締結しました。「子どもの権利条約」を参考にしながら独自に「条例」をつくる自治体もあらわれ、それぞれの地域に合ったかたちでの取り組みが行われています。
条約を批准した国は、定期的にそれまでの取り組みについて、国連に報告を行います。2019年の報告では、国連より改善すべき点として「差別の禁止」「児童の意見の尊重」「体罰」などの指摘を受けています。
「障害者権利条約」は、2006年に採択され、2008年に発効しました。日本は2007年に署名しましたが、障害のある人への差別を禁止する国内法が存在せず、条約の内容を遂行できない状態でした。そのため、障害のある人の権利や福祉についての国内法の整備が集中的に行われることになりました。
2011年の「障害者基本法」の改正では、「障害を理由とする差別の禁止」の項目が加わり、障害があってもなくても分けられず、一人ひとりを大切にする社会(共生社会)の実現を目指すことが明記されました。2012年には障害のある人への支援を定めた「障害者総合支援法」が成立、2013年には「障害者差別解消法」が成立しました。同年に「障害者雇用促進法」も改正され、雇用における差別をなくすための具体的な仕組みも規定されています。このような取り組みを終え、「障害者権利条約」が締結されたのは2014年になってからでした。
「女性差別撤廃条約」「子どもの権利条約」の締結からそれぞれ35年、25年が経過した現在、雇用における格差は未だ存在し、虐待や子どもの貧困が社会問題化しています。「障害者権利条約」については、ようやく試みが始まった段階といえます。
今年は、新型コロナウイルスによる差別や偏見、SNSでの誹謗中傷といった新たな人権問題も発生しました。
人権問題は、人ごとではなくごく身近に存在するということに、改めて気付かされますね。
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」という世界人権宣言の理念を心に留めながら、考え行動することが、今求められています。
参考サイト
法務省外務省国際連合広報センター公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本