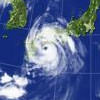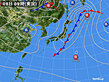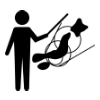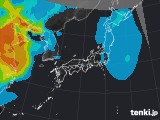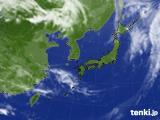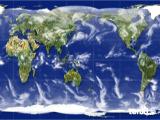今流行中の万葉集では、アジサイを歌った和歌はわずか二首。平安時代の二大文学作品で、植物の記載がやたらに多い枕草子と源氏物語には、一切出てきません。時代が下り、中世になると徐々にアジサイが文献上に登場するようにはなりますが、決して人気が高いとは言えない、影の薄い存在でした。江戸時代は園芸文化がまさに花開いた時代で、ハナショウブ、オモト、ツバキ、サクラソウ、アサガオ、サクラ、ツツジ、ボタン等々、数多くの草木の園芸品種が作出され、それぞれ大ブームの時代を持ちますが、アジサイがブームとなったことは一度もありません。日本人はアジサイを愛してはいなかったし、梅雨の風物でもなかったのです。
アジサイが現在のような熱狂的人気を得るようになった始まりは、東京オリンピック(1964年)も終わり、日本が安定した経済成長路線に入った1960年代後半のこと。1968年に旅雑誌ではじめて鎌倉市の明月院に「アジサイ寺」の通り名が冠され、現在に続くアジサイ人気が始まることになります。
この後日本各地に「アジサイ寺」が出現しますが、それらの「アジサイ寺」に、境内のアジサイの植栽時期の調査をしたところ、岡山の長法寺が1870年ともっとも古いほかは、全てが20世紀以降で、京都の岩船寺が1936年、鎌倉市の覚園寺が1940年代ごろ、元祖アジサイ寺の明月院ですら1951年、千葉県大多喜町麻綿原高原の妙法生寺が1953年という他は、ほとんどが1980年代以降の植栽と判明。「戦後」どころか、昭和も終わろうという時期に、アジサイ観光はメジャー化したのです。
だからアジサイが悪いわけでも価値がないわけでもありませんが、アジサイは日本原産だとはいえ、戦後の欧米化した文化の美意識の中で価値を見出された「新しい花」なのだということをふまえるべきではあろうと思います。実際アジサイは、欧米に渡って「ハイドランジア」として品種が作出されてから見出された欧米由来の花ともいえるわけです。
2011年、アジサイをめぐって海外でちょっとした事件(?)がありました。日本は東日本大震災直後でそれどころではなかったために、あまり話題にはなりませんでしたが、ミュージシャンで大スターのマドンナが、ファンから贈られたアジサイの花束を「アジサイは嫌いなのよね」と憎々しげに語るのをメディアにスッパぬかれ、謝罪を要求されたのでした。マドンナもさるもので、「アジサイさんごめんなさい」という動画を配信、前半でアジサイに涙ながらに謝ったかと思うと、一転アジサイを地べたに叩きつけ、「でもやっぱりアジサイは嫌い!バラが好きで悪かったわね!ここは自由の国よ!」と宣言するオチをつけました。欧米では花の好みは千差万別。日本のように皆でこぞって「桜!」「コスモス!」「アジサイ!」「ネモフィラ!」と熱狂することはないようです。
同じく目立たない日陰者だったキンモクセイや、気味悪いとされていたヒガンバナなどが突如大人気になるのを見ても、花のブームはまさに世につれ人につれ。七変化、七化けと呼ばれるべきなのは、移り気な我々日本人の心のほうなのかもしれません。
参照
日本の花 (松田修 現代教養文庫・社会思想研究会)
植物の世界 (朝日新聞社)
Madonna's love letter to hydrangeas