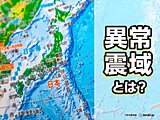街路樹の葉がスカスカに…。アメリカシロヒトリの幼虫が大発生したら…。

こんな葉っぱ、見たことありませんか?
戦後、アメリカからきた外来種。“都市型害虫”とも言われる。

体長は15ミリ、羽を広げると30ミリ。
幼虫は5~7月と8~9月に出現し、幼いうちは、「巣網」という、糸を張り巡らせた巣の中で集団で生活します。1枚の葉に数百匹の幼虫がいることもありますが、成長すると集団行動から離れ、単独で葉を食べます。
成虫は春と夏に、一度に数百個の卵を産みつけます。卵はエメラルドグリーンで若葉と同系色なので、屋外で見つけることはなかなか難しい作業です。サクラやヤナギ、ハナミズキやプラタナスなど、百数十種類の樹木の葉っぱを好みます。
しばしば大量発生して、街路樹や公園の木を丸裸にするので、都市型の害虫といわれます。
葉っぱをムシャムシャ。葉脈をきれいに残して葉肉を食べつくす。

若い幼虫は細い葉脈を食べ残す。
幼い(?)ころの幼虫は、葉のやわらかい部分だけしか食べないので、細い葉脈も食べ残します。葉肉を食べられた葉っぱは細かい葉脈のスジがよくわかるので、理科の勉強に使えるかもしれませんね。
細い葉脈だけが残ったスカスカの葉は茶色く枯れ、まるで何かのオブジェにも見えないこともないような…。でも、そんな葉脈の精巧なオブジェを人間の手で作るとなると、相当な技術が必要です。アメリカシロヒトリならではの、“芸術作品”かもしれません。
毒はなく、人体に影響はない。ヒトリガは、「飛んで火に入る夏の虫」の由来になった。

巣網で兄弟たちと暮らす。
ヒトリガ科の蛾で、名前に「ヒトリ」とつくので、一人で行動するのが好きな蛾だと思われそうですが、漢字にすると「火取蛾」です。多くの蛾は夜行性で、街灯の下などで飛び回っている姿をよく見かけますが、街灯のない昔は、焚き火の明かりに向かって飛んでいき、自ら火に飛び込んで死んでしまうことから、ヒトリガは「飛んで火に入る夏の虫」の由来ともなりました。
巣網を見つけたら、枝の先を切って大発生を防ぐ。無毒の虫に殺虫剤は必要か?

幼い(?)ときは集団行動。
街路樹や公園の樹木など、広範囲で大発生すると、木が丸裸になるだけでなく、幼虫の大量のフンで、あたりが汚らしくなってしまいます。緑を守るために各自治体では、さまざまな工夫がされています。北海道の函館市では街路樹にプラタナスが多く使われていますが、2000年と2014年にアメリカシロヒトリが大発生し、葉の多くが食べられてしまいました。一度発生すると収束するまでに3年はかかるので、市では昨年から、街路樹の枝の刈り込みを2週間ほど前倒しして早めに行い、市内に大発生しないようにしています。
自治体によっては殺虫剤を使うところもあるようです。チャドクガなどの毒虫であれば殺虫剤も必要かもしれませんが、アメリカシロヒトリは無毒です。葉を食べつくすといっても、どうせ冬になれば枯れ落ちる葉なので、人間や土壌に影響のある殺虫剤の散布ははたして必要なのか、疑問を感じる声も少なくないようです。とはいえ、街路樹などが丸坊主になっている姿を見るのはあまりいい気持ちではありません。駆除の方法はどうしたらいいのか、さらには、駆除自体するべきなのかどうか、悩ましい問題といえます。
〈参考:北海道新聞2015年9月29日号函館版26面「並木の枝葉 早く刈り込み アメリカシロヒトリ警戒 プラタナスの食害発生」〉
アメリカシロヒトリの大発生を防ぐために、9月から早々と街路樹の刈り込みをしている自治体もあるようです。みなさんの家の庭の木々も、葉がスカスカになってはいませんか。巣網や葉脈だけの葉を見かけたら、広がるのはあっという間です。駆除するべきか否か、駆除の方法はどうするか…。庭で葉を見つめながら、一人、考えてしまいそうです。